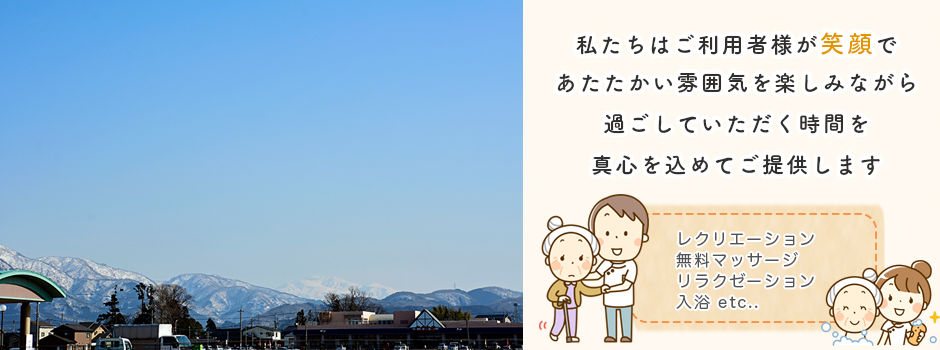しゃちょの読書日記【社長ブログ更新しました】
年の瀬や新年の静かな時間には、普段手が届かない本をじっくり読むのが良い。移動の合間や少しの空き時間でもいいが、たまには腰を据えて、心を落ち着けて本を開く。
そういう時間が、自分の内側を深く見つめる機会になる、、気がする。
今回は、私の書斎の「積ん読」リストの中から、時代を超えて読み継がれている4冊をあらためて手に取った。
1.『タテ社会の人間関係』中根千枝(講談社新書)
「日本人は集団で生きる動物である」という漠然とした感覚は、誰しも持っているだろう。
本書は、その感覚を鋭く切り取って「タテ社会」という明確な言葉に仕立て上げた名著である。
初版が1967年でありながら、現代の日本社会にもそのまま当てはまるのが驚きだ。
読み進めると、まるで今の会社や地域社会を描写しているかのように錯覚する場面が多々ある。
中根は、日本社会の構造を「タテ社会」と「ヨコ社会」に分類し、
集団内での序列や秩序を保つために日本人が無意識に取る行動を丁寧に分析している。
特に印象的だったのは、「日本の集団はタテの関係でまとまり、そこには絶えず上下の意識が存在する」という指摘である。
アメリカ型のフラットな組織が理想とされる現代においても、日本の会社組織や地域コミュニティでは、
役職や年齢による序列が自然と形作られる。
「リーダー」と呼ばれる人も、単なる指示役ではなく、「上との調整役」「下をまとめる存在」として位置づけられるのだ。
私は、これを読んで「なるほど」と膝を打った。
株式会社レイシアにも、確かに「タテ社会」がある。
リーダーシップとは、ただ強く引っ張るものではなく、「場を調和させるもの」だと再認識させられた。
この考え方は、日々の人間関係を円滑にし、チームとしての結束を強めるヒントになる。
長年読み継がれる理由が詰まった、組織や人間関係に悩むすべての人に薦めたい一冊である。
2.『エーゲ 永遠回帰の海』立花隆(ちくま文庫)
「エーゲ海」と聞けば、多くの人が白い壁の建物と青い海を思い浮かべるだろう。
旅情を誘う風景の中で、人は歴史の香りを感じ、そこに「永遠」を見るのかもしれない。
だが、著者が立花隆である以上、ただの旅行記では終わらない。
本書は、エーゲ海の旅を題材にしながらも、哲学、神話、宇宙、生命…と、話がどこまでも広がっていく。
エーゲ海に沈む夕日を眺めながら、人類の起源や死生観について考えさせられる。
そんな「思索の旅」が味わえる一冊だ。
立花が本書で繰り返し語るのは、「時間」に対する独特の視点である。
ギリシャの人々は、時間を「流れるもの」として捉えない。
過去は消え去るものではなく、今この瞬間にも積み重なっているのだという。
この感覚は「永遠回帰」という言葉に象徴される。
つまり、同じ瞬間が繰り返され、過去も未来も「今」の中にあるという考え方だ。
現代社会では「時間=効率」という価値観が支配的だが、ギリシャの人々は時間をもっと大きく、緩やかに捉えている。
「過ぎ去ったものは戻らない」と考える我々には、新鮮であり、どこか羨ましくも感じる世界観である。
私自身、この本を読みながら「時間」に対する感覚が揺さぶられた。
日々の忙しさに流されるのではなく、今ここにある「瞬間」をもう少し大切にしてみようと思う。
エーゲ海に行く予定がなくても、読めばまるでその地を旅したかのような気持ちにさせてくれる一冊である。
3.『禅と日本文化』鈴木大拙(岩波新書)
鈴木大拙の名著を手に取った。
この本は、日本文化に深く根付く「禅」の思想が、どのように芸術や武道、日常の作法に影響を与えてきたのかを探る内容である。
特に心を打たれたのは、「無」の概念についての記述だ。
禅において「無」は、単なる「何もない」という意味ではない。
そこには「豊かな可能性」が内包されており、「無」こそがあらゆるものを生み出す源泉であると説かれる。
大拙はこの「無」を、茶道の作法や剣道の一瞬に例える。
茶室に入り、静寂の中で一服の茶を飲む行為には、目に見えない「無」が存在する。
剣道においても、剣を振り下ろす前の「静寂」の中にこそ、勝負が決する瞬間がある。
この部分を読んで、30代の頃に習っていた裏千家茶道のことを思い出した。
7年間、毎週必ず茶室に通い、長時間の稽古を続けた。
茶道の稽古では、茶を点てることそのものよりも、「その場の空気」をいかに整えるかが重視される。
一つひとつの動作には無駄がなく、所作を通して「心を静める」ことが求められるのだ。
また、それと同時に、10代から20代前半にかけて取り組んでいた極真空手の厳しい稽古も思い起こされた。
極真空手の試合では、相手と向き合う一瞬にすべてが懸かっている。
だが、その一瞬は、ただ力任せに技を出すだけでは生まれない。
むしろ、戦いの中で「無心」になれたときこそ、自分でも驚くような技が出ることがあった。
強さとは、ひたすら相手を圧倒することではなく、「無」の境地で必要最低限の動きに集中することだと感じたものだ。
茶道と極真空手は、一見まったく異なる世界に思えるが、そこに流れる「無の精神」は共通している。
いずれも、余分な動きを削ぎ落とし、自分と向き合うことで初めて本質に近づけるのだろう。
禅の精神は、特別なものではなく、日常のあらゆる場面に息づいている。
例えば、茶室に入るときには「一期一会」という言葉が重んじられるが、
これは「今日という時間は二度と訪れない」という禅の教えに通じるものがある。
大拙は、こうした「今この瞬間を大切にする心」が日本文化全体に影響を与えてきたと説く。
介護の仕事をしていると、ご利用者様との「何気ない会話」や「静かに寄り添う時間」にこそ意味があると感じることがある。
それは、なにも特別な技術を使った介護ではなく、「ただその場にいること」そのものが、ご利用者様の安心に繋がるからだ。
禅が説く「無」の精神は、介護の世界にも通じるものがあると実感している。
本書は決して読みやすい本ではない。
だが、一章ずつゆっくりと読み進めることで、少しずつ禅の世界に触れることができる。
茶道や剣道、あるいは空手といった厳しい道を経験したことがある人には、特に響くものがあるはずだ。
人と接する仕事をしている方には、ぜひ一度読んでほしい名著である。
大拙の言葉は、表面的な「日本文化の知識」を超え、「生きる姿勢」そのものを見つめ直させてくれる。
4.『大局観』羽生善治(角川新書)
「直感とは、膨大な努力の積み重ねの先に生まれるものだ」
羽生善治が本書で繰り返し語る言葉の一つである。
将棋の世界では、「読み」の力が重要視されるが、それ以上に「直感」というものが勝負を左右する場面が多い。
将棋盤の前に座った羽生が、何千通りもの指し手を頭の中で瞬時に思い描き、その中から「これだ」と手を選ぶ。
そのプロセスは、一見して天才のなせる業のように思えるが、
本書を読むと、それが膨大な学びと経験の蓄積から導かれたものだと分かる。
羽生は、自らの直感について「データベースのようなもの」と表現する。
数え切れないほどの対局を重ね、勝ちも負けも味わう中で、
知らず知らずのうちに自分の中に「答えのパターン」が蓄積されていくのだという。
だが、本書で描かれるのは「才能の光」だけではない。
羽生は「失敗」の重要性についても語っている。
「将棋は負けることが多いゲームです。
私が勝率7割であったとしても、10局指せば3局は負けます。そこから学ぶことが最も重要です」
この言葉は、将棋に限らず人生にも当てはまる。
羽生は、敗北を避けるのではなく、「敗北から次の勝ち筋を見出すことが大局観を育てる」と断言する。
一手ごとの失敗に気を取られず、「全体の流れを見る力」が真に必要なのだ。
印象的なエピソードとして、若き日の羽生がタイトル戦で敗れた後、「次の対局は2年後の予定です」と冷静に語った話がある。
普通なら目の前の敗北に打ちひしがれるところだが、羽生は既に「2年後の勝負」に視点を移していた。
「大局観」とは、目の前の結果に一喜一憂せず、長い時間の流れの中で物事を捉える力なのだ。
また、本書では「リスクの取り方」に関しても興味深い考察がなされている。
羽生は「最善の一手が分からないときは、最悪を避ける」という姿勢を貫く。
攻めるべきか守るべきか迷う場面では、ギリギリの攻防にこだわるのではなく、「負けない選択」を取ることが重要だという。
これは経営や人生の分岐点においても応用できる考え方だろう。
何か大きな決断を下す場面では、あえて「大きく勝ちに行く」のではなく、
「最悪の事態を避ける」という視点で選択することが、結果的に最善の未来へと繋がるのかもしれない。
本書を読み終えると、自分の中にも少しだけ「大局観」が芽生えたように感じる。
日常の小さな悩みや選択も、一歩引いて俯瞰してみると、見えてくるものが変わってくるのだ。
将棋を知らなくても大丈夫だ。
人生や仕事に迷いが生じたとき、羽生善治の「大局観」は、静かに背中を押してくれるに違いない。
2025年01月07日 18:52