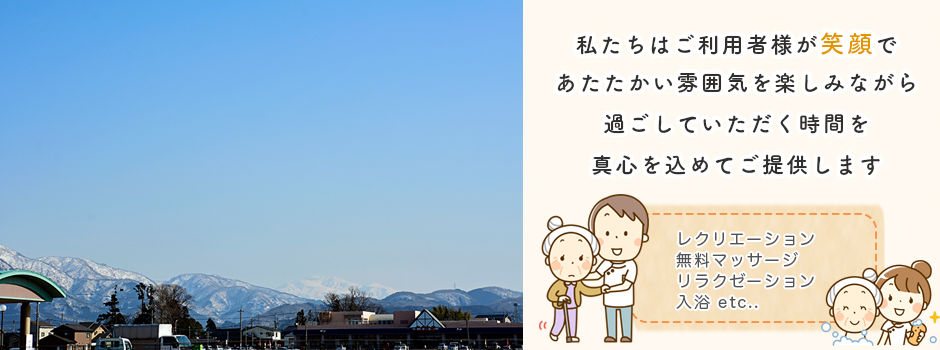しゃちょの読書日記【ブログ更新しました】
『アメリカのプロレスラーはなぜ講道館柔道に戦いを挑んだのか 大正十年「サンテル事件」を読み解く』(藪耕太郎著・集英社新書)書評
結論から言えば――これは、格闘技史に潜む“原点の迷宮”を、事実と記録で一つひとつ照らしていく、知的にして緊張感あふれる一冊だ。
1921年、大正十年に起きた「サンテル事件」。アメリカの職業レスラー、アド・サンテルが講道館柔道に挑んだとされるこの出来事は、長く伝説や誤解に覆われてきた。
本書はその霧を晴らす。
著者は体育・スポーツ史研究者の藪耕太郎氏。豊富な一次資料と海外アーカイブを駆使し、俗説を徹底的に削ぎ落としていく。
読後には、「日本の武道」と「アメリカのレスリング」が出会った瞬間の空気が、静かに立ち上がってくる。
――なぜ、アメリカのレスラーは講道館に挑んだのか。藪氏の答えは単純な「強さ比べ」ではない。
20世紀初頭、柔術や柔道はアメリカで異種格闘技としての人気を集め、移民社会のなかで日本人の誇りと結びついていた。
アド・サンテルはその潮流の中に登場する。
彼はキャッチ・アズ・キャッチ・キャン――関節技や抑え込みを得意とする実戦型レスラーであり、柔道家たちとの対戦を“興行”として行った。
だがそれは単なるショーではなかった。
柔道が「教育」や「徳育」の道として整えられていく時代に、サンテルは「力の見せ物」として立ちはだかったのである。
著者は、当時の新聞、雑誌、興行記録を丹念に読み解き、事件の実相を再構成している。
事件の中心となった試合は、東京・靖国神社の相撲場を含む特設会場で行われたとされ、嘉納治五郎はこれを好まなかった。
講道館の統制の外で柔道家が出場したことが問題視され、のちに「講道館柔道の規律を乱した」として処分が下された。
これが、のちに「サンテル事件」と呼ばれる。著者は「誰がどこで何をしたか」を、推測ではなく史料で裏づける。
新聞の断片、英字紙の記事、当時の講道館関係者の記録を照合しながら、「講道館がなぜ沈黙したのか」「なぜ世間が熱狂したのか」を社会的文脈の中で描き出す。
そこには単なる勝敗の物語ではなく、メディア・商業・国民感情が交錯する、ひとつの“時代の現象”がある。
本書の魅力は、事件を「興行史」と「統治史」の両面から描く点にある。
柔道は嘉納の理念のもとで教育体系に組み込まれ、「スポーツの近代化」と「道徳の近代化」を担う存在となっていた。
一方、アメリカのプロレスは「真剣と見世物のあいだ」で拡張を続け、商業的な成功を収めていた。
その二つが日本の土の上で正面衝突した――この構図こそが、事件の本質だと藪氏は説く。
勝敗の記録にこだわらず、どのように語られ、誰がそれを望み、社会がどう受け止めたのかを分析する。その冷静さが、逆に読む者の血を熱くする。
著者は、サンテルを“破壊者”として神格化もせず、嘉納を“聖人”として理想化もしない。
史料の届く範囲で両者を描き、分からない部分は分からないまま残す。
だからこそ、事件が持つ「わからなさ」のリアルが立ち上がる。
サンテルの試合経歴、興行スケジュール、新聞報道の温度差――いずれも著者が丹念に検証した成果だ。
これまで“伝説”として語られてきた部分を史料に引き戻し、当時のメディアと観客の期待がどう試合を物語化していったかを浮かび上がらせる。
特筆すべきは、藪氏が「異種格闘技」という概念そのものを問い直している点だ。
日本ではアントニオ猪木の挑戦がその象徴とされるが、著者はサンテル事件をその「直接の原点」と断定せず、「異種格闘技的な想像力」がすでにこの時代に芽生えていたと位置づける。
すなわち、講道館が掲げた「道」と、アメリカが体現した「見せる格闘」の文化が初めて真正面から出会った場こそが、1921年だったという視点である。
ここに、単なる懐古ではない“現代への問い”が生まれる。
本書を読むと、嘉納治五郎の判断がどれほど繊細だったかが見えてくる。
柔道を教育制度に組み込む努力を続けていた嘉納にとって、商業的な試合は理念の根幹を揺るがしかねない。
一方で、門下生の中には実戦志向の者もおり、柔道を「強さ」で証明したいという情熱もあった。
事件は、まさにその分岐点で起こった。
著者は、嘉納の統治と門下生の行動を対立ではなく構造として読み解き、「教育としての武道」と「興行としての格闘」がぶつかる地点を、社会史として描いている。
藪氏の筆は、学術的でありながら平明だ。
細部を描きながらも、リズムがある。引用は必要最小限に抑え、史料を語らせる。
時に静かに、時に鋭く、100年前の光景が浮かび上がる。靖国という場所性への踏み込みも節度を保ち、政治的解釈ではなく史料的距離を貫いている。
だからこそ、読者は事件の輪郭を落ち着いて追える。歴史の「語られ方」を問う誠実さが、全体を貫いている。
この本が教えるのは、「伝説の裏側にある人間の現実」だ。
誰もが自分の信じたい勝敗を語り、やがてそれが“史実”になっていく。
本書はその過程を丁寧に逆算し、「何が事実で、何が物語だったのか」を明らかにしていく。
読者は“勝負の記憶”そのものが社会的な生成物であることを知るだろう。
そして、現在のMMAやプロレス文化を理解するうえでも、この事件を抜きに語れない理由が見えてくる。
ただし著者は、そこに安易な系譜や英雄譚を結ばない。むしろ、「異種格闘技とは、社会が自らの境界を試す儀式だった」と指摘する。
その冷徹さにこそ、格闘技史の本質が宿る。
本書の読後感は、不思議な静けさだ。
勝敗の興奮ではなく、記録と記憶のすき間に漂う余韻。100年前の出来事をここまで精緻に再構成した研究は稀だろう。
格闘技ファンはもちろん、スポーツビジネスやメディア史、武道教育の視点からも必読である。
事実をもって伝説を見直す――それが、本書の最大の魅力である。
最後にひと言。
事実を積み上げる筆致は冷静なのに、ページの奥には熱がある。
伝説の霧を払い、もう一度語り直す。その営みこそ、知の格闘である。
本書はそのリングの中央に、確かな一歩を刻んでいる。