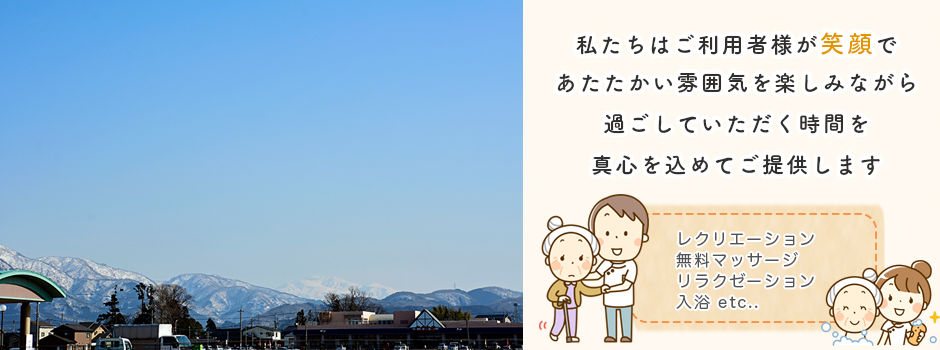しゃちょの読書日記【ブログ更新しました】
『大岡越前守忠相』(大石慎三郎著)を読んで
この本を手に取るとき、私は一般的な偉人伝や、テレビ時代劇がつくり上げてきた「名奉行像」をなぞるだけの気持ちではなかった。
むしろ、「名奉行・大岡越前」とは何か、その虚像と実像を、現場主義の視点から一度すべて疑ってみたいという思いがあった。
著者・大石慎三郎は、いわゆる美談や伝説に安易に流されることなく、膨大な史料や町奉行所の実務記録を細かく検証する。
その中から見えてくるのは、理想化された人物像ではなく、江戸という巨大都市を、リアルな「現場感覚」でマネジメントした一人の行政官としての忠相である。
江戸の人口は当時世界最大級。
その都市にあって、犯罪、火事、飢饉、疫病など、現代の大都市にも通じる社会問題が絶え間なく発生していた。
忠相は、その都度、既存の制度や法令に頼るだけでなく、現場で何が起きているかを自ら観察し、関係者の声に直接耳を傾けることで、柔軟かつ大胆な対応を重ねていった。
たとえば大飢饉のときには、幕府の規定では救済できない人々に対して、自分の裁量で救いの手を差し伸べることもあったという。
こうした「制度と現実のねじれ」に直面したとき、忠相は決してマニュアル通りの対応で済ませようとせず、時には上司や既得権益との摩擦も恐れず、現実的な選択を積み重ねていく。
その姿勢は、現代の経営者や管理職にも直結する“判断力”と“現場主義”の重要性を教えてくれる。
また本書では、忠相がさまざまな対立や矛盾に悩みながらも、「善悪二元論」で割り切れない複雑な人間関係の中で、
折衝やすり合わせを何度も繰り返してきた様子が、具体的なエピソードを交えて描かれる。
部下の反発や不満、町人とのトラブル、上層部からの政治的圧力――これらにいかに向き合い、バランスを取り続けたのか。そのプロセス自体が、現実の組織運営の苦しさと面白さを体現している。
印象深いのは、忠相が「名奉行」として歴史に名を刻んだ理由が、決して“天才的な判断力”や“完全無欠の人格”にあったわけではないという事実である。
むしろ、泥臭く現場に入り、失敗や批判も引き受け、諦めずに細部を調整し続ける「地道な粘り強さ」「実直な姿勢」にこそ、真のリーダーの条件が見出せる。
本書を読み終えたあと、私は「リーダーとは何か」という問いに対して、以前よりもはるかに多面的な視野を持つことができたと感じる。
人は決して神話のように完璧ではない。困難や矛盾と向き合いながらも、現場で悩み、行動し続ける。その過程こそが、未来の社会を形づくるのである。
過去を掘り下げるとは、実は自分たちの未来を考える作業そのものだ、と強く実感した一冊である。
北國文華という雑誌を手に取るたび、「地域雑誌」というジャンルに対する自分の固定観念が揺さぶられる。
今号の特集「山城が語る北陸乱世の攻防」は、タイトルだけ見れば地元歴史ファン向けに思えるかもしれない。
しかし実際には、スケールが大きく、知的刺激と発見にあふれた一冊である。
まず目を引くのは、山城を単なる合戦や武将伝説の舞台としてではなく、
「地形」「気候」「交通」「民衆の生活」「宗教」「経済」など、多様な観点から総合的に分析している点である。
なぜその場所に城が築かれ、時代とともにどのように変遷・消滅していったのか。
その背後には、戦国の権力闘争や合戦だけでなく、自然条件や地域社会の暮らし、外部勢力との複雑な関係があることが見えてくる。
さらに、実際に現地に足を運び、山城跡の地形や遺構を観察し、住民の伝承や新しい発掘成果も積極的に誌面に盛り込んでいる。
「歴史を自分の足で掘り起こす」という現場主義の姿勢が、この雑誌の大きな魅力だ。
また、連載エッセイや短編小説、研究者や地元の郷土史家によるリポートなど、多様な書き手による記事が並び、それぞれの視点から歴史の多面性を描き出している。
これにより、歴史が“知識の集積”ではなく、「いま、ここを生きる自分たちの問題」として立ち現れてくる。
山城というテーマを通じて、歴史の勝者の物語だけではなく、名もなき人々、消えた城、残された地形、そうした“無数の小さな声”に光を当てる――
『北國文華』は、郷土の誇りやロマンだけでなく、「歴史を知るとはどういうことか」「自分たちはどんな地域社会をつくっていきたいのか」といった根源的な問いに向き合うための道標となる。
この雑誌を読み終えたとき、自分自身が生きている場所や日々の仕事、その意味までもが、新しい光の中で見えてくる。
歴史や地域に関心のある人はもちろん、今を生きるための知恵や視点を養いたいと考えるすべての人に、ぜひ一度手に取ってもらいたい一冊である。