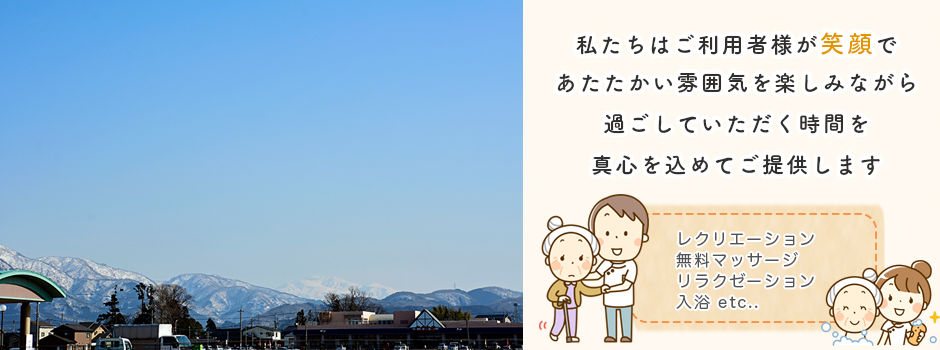しゃちょの読書日記【ブログ更新しました】
書評①『「鎖国」を見直す』(荒野泰典著、岩波現代文庫)──「閉ざされた日本」という思い込みを、そろそろ手放してみないか
「江戸時代の日本は、世界から完全に閉ざされた“鎖国”状態にあった」
これは、おそらく多くの人が学校で習い、疑うことなく受け入れてきた歴史の“常識”である。
だが、それは果たして本当に正しいのだろうか?
本書『「鎖国」を見直す』は、その常識にゆるやかに、しかし明確に異議を唱える。
著者の荒野泰典氏は、日本と諸外国との交流史を専門とする歴史学者。
本書では、江戸時代における日本の対外政策を、実際の史料と事実に基づいて読み解きながら、「鎖国」という言葉のもつ単純すぎるイメージを一つずつ丁寧に解きほぐしていく。
まず最初に押さえておきたいのは、私たちがごく当たり前のように使っている「鎖国」という言葉は、江戸時代当時には存在していなかったという事実だ。
幕府が「鎖国政策」と名付けたわけでもなく、当時の人びとが自国を“鎖している”と自認していたわけでもない。
「鎖国」という言葉が日本で使われ始めたのは、明治時代に入ってからのこと。
海外に開かれた近代国家を目指す過程で、「江戸時代=世界に背を向けた閉鎖的な時代」と位置づけるために、後の時代がつくったレッテルだったのである。
この視点だけでも、すでに「歴史の見方がひっくり返るような感覚」を覚える読者も多いはずだ。
では実際、江戸幕府はどのように外交・貿易を行っていたのか?
本書では、出島を通じてのオランダ・中国との継続的な貿易、朝鮮との通信使の往来、琉球王国や蝦夷地(アイヌ)を介した文化的・経済的交流など、
日本が複数のルートを通じて世界とつながっていた様子が具体的に描かれる。
もちろん、貿易や渡航は厳しく制限されていたが、それは「完全に断っていた」というより、「必要な相手と、必要な方法で」関係を保っていたというのが実態である。
特に注目すべきは、外交や貿易が単なる“物のやり取り”にとどまらず、文化や知識の交流としても機能していた点だ。
たとえば朝鮮通信使との詩文の交換、贈答品のやり取り、儒学思想の共有など、精神文化を通じた国際的な対話が行われていた。
オランダから伝わった西洋の自然科学や医学も、蘭学として国内に根付き、知的発展の礎となった。
「断絶」ではなく、「慎重に選ばれたつながり」が、江戸の日本には確かに存在していたのである。
そしてもう一つ、本書が重要視するのは、なぜ幕府がこのような“制限付きの開放”を選んだのかという点だ。
それは、単なる排外主義や恐怖からではない。社会の安定を守り、権力構造を維持するために、情報や人の流れを慎重に管理しようとした結果だった。
全てを開くのではなく、コントロール可能な形で関係を持ち続ける──その姿勢は、現代社会における国家戦略や情報制御の考え方にも重なる。
あらすじ:
「鎖国」という言葉は、実は江戸時代には存在しなかった。
本書はその出発点に立ち、幕府がどのように対外関係を制御し、どのように世界と接していたかを、多くの史料と具体的な事例をもとに描いていく。
オランダや中国との貿易、朝鮮通信使の来訪、琉球や蝦夷地を通じた交流など、日本は決して孤立していたわけではなかった。
その実態を読み解くことで、「閉ざされた国」という従来のイメージを超えた、より柔軟で知的な日本像が見えてくる。
本書は、「歴史の常識」を疑うという意味で、知的な刺激に満ちた一冊である。
江戸時代は決して“閉ざされた時代”ではなかった。
むしろ、情報・技術・文化を取り入れながら、自国の安定と発展を図ったバランス感覚にあふれた時代だったと、著者は語る。
「鎖国」という単語の持つ、曖昧で強いイメージを手放すことで、私たちは過去の日本を、より柔軟で多面的にとらえ直すことができる。
そのとき初めて、「日本とは何か」という問いに対して、新しい答えが見えてくる。
歴史をただ“学ぶ”のではなく、“考え直す”こと。
この本は、それを始めるのに最良の一冊である。
書評②『大西洋漂流76日間』(スティーヴン・キャラハン著、早川書房)
これは、76日間に及ぶ漂流のサバイバル記録でありながら、読む者の心を静かに、しかし深く揺さぶる「人間存在の証明」である。
1982年、著者スティーヴン・キャラハンは、自作の小型ヨットで単独の大西洋横断航海に挑んだ。
ところが出航から数日後、ヨットは嵐により沈没。彼はわずか2メートル四方ほどの救命いかだに乗り移り、装備も限られる中で、広大な海に投げ出される。
彼の手元にあったのは、ソーラースティル(太陽光で淡水をつくる装置)、釣り道具、少量の食糧、そして日記帳。
それ以外、誰もいない。どこにも陸地は見えない。時間の感覚も曖昧になっていくなかで、彼はただ“生きること”と向き合う。
食料が尽きれば魚を捕り、喉が渇けばわずかな水滴を集める。
ときにはサメに囲まれ、嵐に打たれ、飢えと孤独と幻覚に襲われる。
しかし彼は、あきらめない。
なぜなら、この本質的な問いが彼の中にあったからだ──「私はまだ、生きていたいのか?」
本書の魅力は、単に極限状態のスリルや工夫を描いているだけではない。
むしろ、極限の中でこそ浮かび上がる、“人間らしさ”の輪郭が息づいている。
魚と対話し、鳥の影を追い、波間の星に祈る。彼は海と敵対するのではなく、海に問いかけ、語り合いながら生き延びていく。
文章は驚くほど冷静で静謐。
感情を煽るような表現はほとんどない。
それなのに、行間から滲み出るのは、命の重みと、生きることの尊さだ。
読後、しばらく言葉が出てこなかった。
ページを閉じても、彼が見た海の色と、夜の冷たさと、孤独の手触りが、こちらの胸にいつまでも残っていた。
あらすじ:
スティーヴン・キャラハンは、自作のヨットでフランスを出航し、大西洋横断に挑んだ。
だが航海の途中、嵐によりヨットが沈没し、彼は救命いかだでの孤独な漂流生活を余儀なくされる。
頼れるものはわずかな装備と経験、そして自らの判断力と意志だけだった。
魚を釣り、雨水を集め、暑さと寒さ、飢えや孤独と向き合いながら、76日間を大海原の上で生き延びた。
そして最終的に、カリブ海で漁船に発見され、奇跡のように生還を果たす。
本書は、単なるサバイバルの記録ではない。
自然と対峙する中で、人はどこまで一人でいられるのか、なぜそれでも生き続けようとするのか、という問いが静かに立ち上がる。
読む者は、気づけば彼と共に海を漂い、自分自身の内面を深く見つめている。
失いかけていた感覚や、置き去りにしていた思いを、そっと拾い上げるような読書体験である。
2025年05月24日 13:36