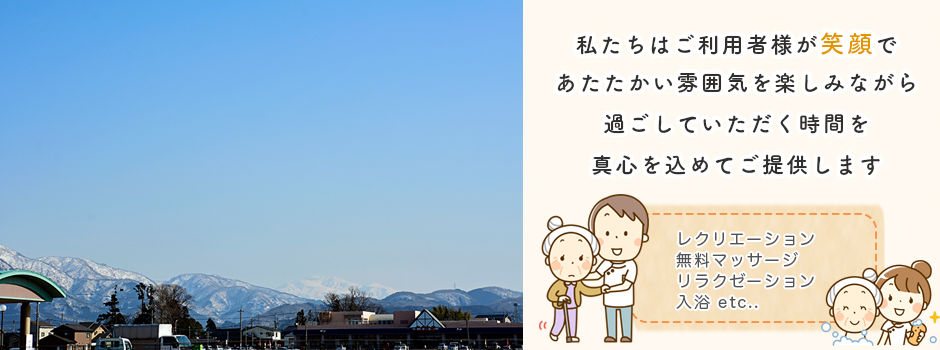しゃちょの読書日記【ブログ更新しました】
①『批評理論入門―「フランケンシュタイン」解剖講義』廣野由美子著(中公新書)「フランケンシュタイン」を最後に読んだのはいつだったか――。
高校時代、文庫本であらすじをなぞった記憶、あるいは怪物が「グワー」と叫ぶ古い映画のイメージしかない方も多いかもしれない。
だが、廣野由美子の『批評理論入門』を手にした瞬間、この“怪物文学”が一気に知的なラビリンスへと変貌を遂げる。
この本は、「文学をもっと深く読みたい」と願うすべての読者に向けた、鋭く、それでいて親しみやすい批評理論のガイドである。
取り上げる理論は、精神分析批評にフェミニズム、新歴史主義からポストコロニアル批評まで、そうそうたるメンバーが並ぶ。
だが、廣野氏の筆は決して威圧的ではない。理論の骨格をきちんと押さえつつも、読者の頭の中にすっと入ってくる。
たとえば、「怪物」はフロイト的に読むと“抑圧された欲望”のメタファーになり、
フェミニズム批評では「男が男だけで生命を創ろうとした代償」と解釈される。
新歴史主義なら、18世紀末の科学革命と社会不安が影を落とす。
ポストコロニアルな視点では、「西洋が他者に投影した恐怖」として怪物を読むこともできる。
同じ物語なのに、視点が変われば意味がガラリと変わる。
これこそが批評の面白さであり、「読む」ことの奥深さだ。
特筆すべきは、廣野氏が理論を「上から振りかける道具」としてではなく、「感覚を深めるためのレンズ」として使っている点である。
読者が「ここ、なんだか変だな」「うまく言葉にできないけど気になるな」と思ったその感覚を、理論で言語化していく。
つまりこの本は、「あなたの直感は間違っていない。その奥に、意味がある」と語りかけてくれるのだ。
構成も秀逸だ。一つの作品を繰り返し読み直しながら、各理論を重ねていく手法は、知識の積み上げだけでなく、“読み方そのものが変わっていく快感”を読者に与える。
まるで同じ風景を、朝焼け、夕暮れ、霧の中、真夜中の月明かりと、さまざまな光で見直しているような感覚がある。
理論に初めて触れる人には親切であり、すでに知っている人にとっては再発見の連続。
大学の教科書よりずっと読みやすく、それでいて内容は驚くほど濃い。
“教養としての批評理論”を一冊で体験したい人、
“読むこと”を自分の中でアップデートしたい人、
あるいは、ただ「フランケンシュタイン」を違う角度から眺めてみたいという人にも強く薦めたい。
最後にひとつ。
この本を読み終えたとき、あなたの読書人生の風景は確実に変わっている。
もう「ただ読んで、いい話だった」では済まされない。
目の前の物語が、「なぜ、いま自分に届いたのか」という問いへと変わるからだ。
それは、ちょっと怖い。でも、すこぶる面白い。
② 今西錦司『生物の世界』(講談社学術文庫)
「生きものたちは、闘ってなどいなかった。」
――“競争のない自然観”を提示した、静かで深い一冊
自然界と聞いて、多くの人がまず思い浮かべるのは「弱肉強食」や「生存競争」といった言葉かもしれない。
ダーウィンの進化論が広まって以来、自然は過酷な選別の場であり、強い者が生き残るというイメージが、私たちの常識になっている。
だが今西錦司は、この本の中で、その「常識」に異を唱える。
『生物の世界』――それは生物学の専門書ではなく、自然観察を通して紡がれた、ひとつの哲学的エッセイである。
そしてそこにあるのは、「競争ではなく共存」「淘汰ではなく棲み分け」という、やわらかくも芯のある自然観だ。
■ 森で出会った生きものと“なじむ”ということ
今西錦司は学者であると同時に、登山家であり、フィールドワーカーだった。
彼の言葉は、机上の理屈ではない。すべて、山や森や川で実際に観察してきた生きものたちの姿から生まれている。
たとえば、ヤマネという小動物が木のうろに巣を作り、静かに眠る姿。
あるいは、川の流れに応じて、イワナは上流、ヤマメは中流、アユは下流に暮らすといった、生きものたちの“すみ分け”の現場。
今西はそれを「生きものたちが、あらかじめ相談していたかのように、ぶつからずに棲み分けている」と描写する。
この視点は、私たちが日常的に刷り込まれてきた「自然は競争社会」というイメージを覆す。
今西は繰り返しこう語る――
「生きものは環境に“適応”しているのではない。“なじんで”いるのだ」と。
適応とは、受け身の関係である。だが、なじむという言葉には、もっと能動的で、双方向的な関係が感じられる。
生きものが環境を選び、自分らしい場所を見つけて生きる。
それは、まるで自然との対話のようなあり方である。
■ 棲み分けの思想と、その静かな示唆
『生物の世界』では、「棲み分け理論」という言葉こそ正面から解説されてはいない。
だが、今西の考え方の中核には常に「衝突を避け、共に生きる」ことへの深い洞察がある。
たとえば、第6章では、イワナとヤマメが同じ川の中で、自然に領域を分けて生きていることが描かれる。
今西はそれを、ただの生態の事実としてではなく、自然が無理のない形で共存のバランスをつくり出している証拠として受け止める。
また、ニホンザルの群れについて書かれた章では、群れの中にある役割や秩序、無言の連携について観察している。
「群れは、一匹一匹の集まりではなく、一つのまとまりとして動いている」とする今西の見方は、後に彼が人類進化論で展開する「集団進化論」にもつながっていく。
■ 難しい理屈ではなく、“生きものを見るまなざし”の本
この本を手に取った人がまず驚くのは、その読みやすさかもしれない。
文体は平易で、難解な専門用語は出てこない。学術書ではなく、まさに「自然を語る本」なのである。
しかし、その平易さの奥には、非常に深い問いが潜んでいる。
「生きるとはどういうことか」
「人間は自然の中で、どうあるべきか」
そうした問いが、静かに、しかし力強く、読者に投げかけられてくる。
今西は、生きものを“観察対象”としてではなく、“生きる仲間”として見ている。
だから彼の言葉はどこかあたたかく、押しつけがましさがない。
そしてそれが、本書を読む人の心にじんわりと届いてくる。
■ 現代を生きる私たちへ、今西からのメッセージ
『生物の世界』が刊行されたのは1967年。
だが、60年近く経ったいま読んでも、まったく古びていない。むしろ、今の時代にこそ必要とされる本だと感じる。
効率や成果、競争ばかりが求められる社会の中で、「棲み分け」や「なじむ」という言葉は、どこか優しく響く。
誰かと争うことなく、自分に合った場所で静かに生きるという選択。
それは、私たち人間にも許されているはずの生き方なのではないか。
この本には、派手な理論も、目新しい情報もない。
だが、ページを閉じたあと、自分の中にひとつの“まなざし”が育っていることに気づく。
それは、「生きものを敬い、自然に耳をすます」という、ごく当たり前の感覚だ。